実は、紙が日本人の安全意識の源だった⁉という話。
昔の日本家屋って、壁と柱を取っ払うと、後はフスマと障子だけってものが多い気がします。

言い換えると、日本家屋は、壁と柱以外は紙でできているということです。
時にはそこが赤の他人同士の寝泊まりの空間となるから面白いものです。
西洋や米国から見たら「えっ、紙でできてるの?そんなんで安全なの?」という感じかもしれません。

ですが、そこには日本人ならではの、紙に対する考え方があるように思えます。
紙というものは、”少しでも傷が付けば元には戻らない”という特徴を持っています。
なので紙に接するには「緊張感」が伴います。この話は【紙を見たら衛生と思え⁉⁉】で話しておりますのでこの機会に是非ご覧ください。
先日、特殊な色紙を買いに某雑貨屋に行った際、レジの店員さんの紙の扱いには驚きました。
その店員さんに購入したい色紙を何枚か重ねて渡したんです。そうしたら、その店員さん、札束を数える時のように紙を折りながら数えだしたんです。長い付け爪も相まって、紙の端が見事に折り曲がってしまいました。
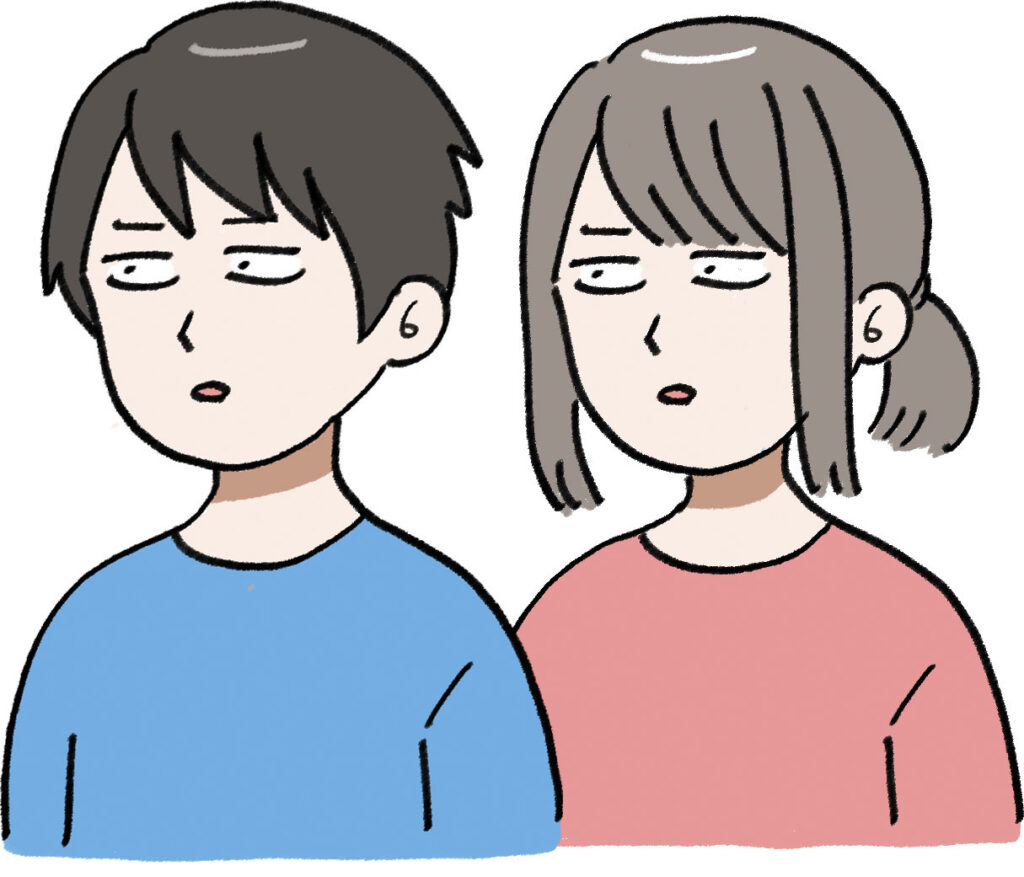
さすがに取り換えてもらいましたが、紙に対する緊張感は人によりけりというところもあるようです。
それでも、昔の日本家屋を見ると、日本人は、昔から紙に対する緊張感を大切にしていた民族だったように思えます。
他者に対して物理的に強固な壁を引く代わりに、フスマがまるで魔法陣のように、自分と相手との仕切りの役割をしていたのでしょう。
そこでは、決して相手への配慮を忘れない。だから意識の上での安全が保たれる。壁で仕切ってしまっては隣人は何者なのかも分からないが、紙一枚挟んだ相手であればお互いが分かっているという緊張感のもとに日常的に安全を共有できたのかもしれません。
安全な製品を作るには、丁寧な作業が求められます。そこにはある種の緊張感が伴います。
ペーパーレス化が進む現代は、一昔前に比べると、安全を意識する機会が失われているのかもしれません。
例えば、品質管理業務を学ぶ際には、改めて紙の緊張感に触れてみるのも良いかもしれません。

