コロナ以降、「衛生」は、誰もが日常的に耳にする言葉となりました。

コロナ以前は、医療関係か食品関係などが使うくらいで、あまり聞きなれた言葉では無かったように記憶しております。(もしかしたら、自分の専門だからそう感じるだけかもしれませんが)
改めて衛生という言葉を眺めると、「生を衛(まも)る」と書きますので、それは、死と直結する言葉という印象も湧きます。
衛生が生活の中で当たり前のように聞かれるということは、その分、私たちの生活の中で「死」が以前よりも身近になった、ということなのかもしれません。
「生」に意味を付けるのと同じように、
身近になった「死」にも、意味を付ける…付けたがるのが人間です。
センス・オブ・ワンダー
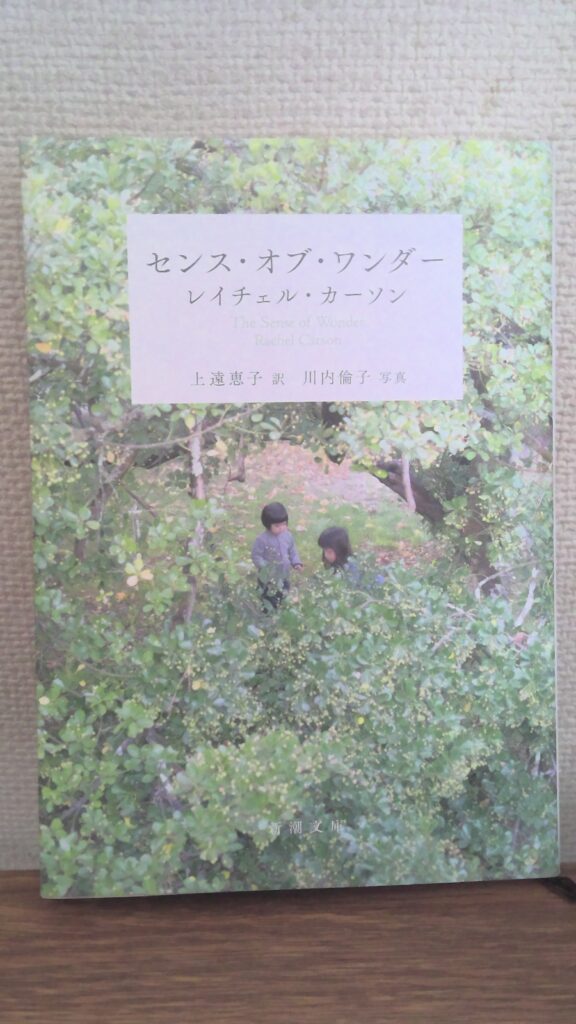
直訳すると、”驚きの感覚”。レイチェルカーソンの名著です。
小さい頃、公園の水たまりで泥まみれになったり、キバチやダンゴムシを取ったりして、驚きと感動で満ち足りていました。

ただそれだけで良いわけで、そこに意味があったのか、意味が無いと本当に幸せではいられないのか不明なんです。
ひょっとしたら、生死に意味を付けることで、経済活動を回し、文明を永続させるような社会が作られているのかもしれないな…と。
死の意味を問われ、もし悩む自分がそこにいたら、

あれこれ思いを巡らせず、
「センス・オブ・ワンダーが足りてないんじゃない?」

それだけを自問してみるのも良いのではないでしょうか。
茨木のり子さんの「自分の感受性くらい」という詩が大好きなので載せます。
——————————————————–
【自分の感受性くらい】
ぱさぱさに乾いてゆく心を
ひとのせいにはするな
みずから水やりを怠っておいて
気難かしくなってきたのを
友人のせいにはするな
しなやかさを失ったのはどちらなのか
苛立つのを
近親のせいにはするな
なにもかも下手だったのはわたくし
初心消えかかるのを
暮しのせいにはするな
そもそもが ひよわな志にすぎなかった
駄目なことの一切を
時代のせいにはするな
わずかに光る尊厳の放棄
自分の感受性くらい
自分で守れ
ばかものよ
詩人:茨木のり子
———————————————————
これって、まさにセンス・オブ・ワンダーですよね。

※ここでは、「死に意味を付与しない文明は歴史上滅んでいる」という文明論は一旦おいておきます

